2025/03/25(火)
認知症が発覚した後の生前贈与について

ようやく暖かくなり始めて勝手にウキウキしてます…太田です!!
今回は生前贈与についてお話しをさせて頂ければと思います。
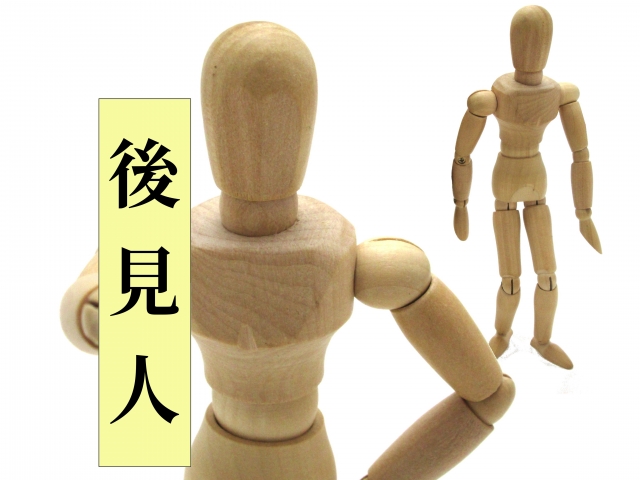
高齢化社会といわれる昨今、2025年には4人に1人が認知症になるといわれているのをご存じでしょうか。ご家族の誰かが認知症になってしまうことも十分考えられます。
高齢の両親がいて相続についてお考えの方は、親が認知症になってしまった場合の相続について学んでおいたほうがよいでしょう。
認知症を発症した親が作成した遺言書や、生前贈与の手続きはどのような問題や注意点があるのでしょうか。
親が認知症であっても、状況によっては法的な手続きをすることが可能です。
この記事では、認知症になった親の遺言作成や生前贈与について、問題点や注意点を解説してまいります。
◎認知症と相続トラブル
遺言書や贈与というものは、意思能力が無いと無効とされる場合がございます。
遺言を書いたり贈与をした当時に認知症であると、意思能力がないとされる場合がありますので、無効にならないよう注意が必要です。
せっかく遺言書や生前贈与の準備をしていても、無効となってしまったことで相続について家族間でトラブルになる可能性も考えられます。
また、認知症であったことを理由に、贈与を受けていない家族の誰かが後から無効を主張するかもしれません。認知症の方が行う贈与は注意が必要です。
◎認知症の進行度によっては生前贈与可能なケースもございます
認知症になってしまうと生前贈与は全くできなくなってしまうかというと、そうではありません。一定の条件のもとであれば可能なのです。
例えば、親から生前贈与を受けるとき、親の意思能力が重要となります。
意思能力が無いと判断されると、財産を処分する能力がないとみなされ、生前贈与が無効となってしまいます。
◎軽度の認知症の場合の生前贈与
軽度の認知症であれば、意思能力があると認められる場合があります。しかしながら、軽度だからといって家族など素人が適切な判断をすることは極めて難しいことです。
問題ないと考えて安易に贈与契約書を作成したものの、無効となってしまう可能性もあります。安全な対策としては、やはり医師と面談をして、遺言書の作成や、生前贈与行為が可能かどうか相談をすることです。もし、可能と認められれば、カルテや診断書にその旨を記録してもらいましょう。
後からトラブルが起きたとしても、証拠として提出できる準備をしておくのが得策です。
◎最後に
ここまでご説明をしてきましたとおり、認知症の親から生前贈与をしてもらう上で重要になることは、意思能力の有無の判断です。医師に判断してもらうことは、後々のトラブルを防ぐためにも重要なことです。素人判断をせずにきちんと記録を残してもらいましょう。
不動産の査定はコチラからどうぞ!
今なら査定+来場でクオカードプレゼント中です♪


